
[:ja]鶴見小野編集部
つるみおのへんしゅうぶ
町の人が編集部員となり、鶴見小野エリア、鶴見区周辺での取り組みや暮らすひとなどを取材し、SNSなどで拡散するローカル編集部。最初は講座をひらき、プロの編集者や美術家と一緒に文と写真の表現を、映像作家や音楽家と一緒に映像で表現することのワークショップを行ないました。講座を通して完成した取材記事やプロモーションミュージックビデオは「編集部マガジン&ムービー」の中で公開中です。今後も町の魅力を発信する多世代・多文化の部活動として続けていきます。
参加アーティストのプロフィール PROFILE
齊藤真菜 さいとうまな/ライター・編集者
横浜市鶴見区出身・在住。イギリスの大学卒業、NPOを経て現在はフリー。地域の文化・商業情報について執筆する傍ら、「藤棚デパートメント」内の間借り本屋「Arcade Books」で、本のセレクトや販売をしている。
大洲大作 おおずだいさく/美術家
写真を通して人々の生活を写し出す。最近は、列車の車窓から見える風景の中に光や人々の営みを見つけて切り取り、実際の車窓に投影する方法で作品を発表している。
内海拓 うちうみたく/映像作家
クロマキーや映像を切り撮った素材を合成し組み合わせたコラージュ映像や、音楽制作チームのMV制作に取り組む。映像の面白さだけでなく、鑑賞する行為全体に影響するような創作を心がけている。
大野志門 おおのしもん/音楽家
ピアノ演奏や、ラップによる楽曲制作、ライブ活動を行う。音楽の中でも、ジャンルにとらわれず活動範囲を広げるような挑戦をしている。ピアノ演奏では現代音楽を主に行う。[:]
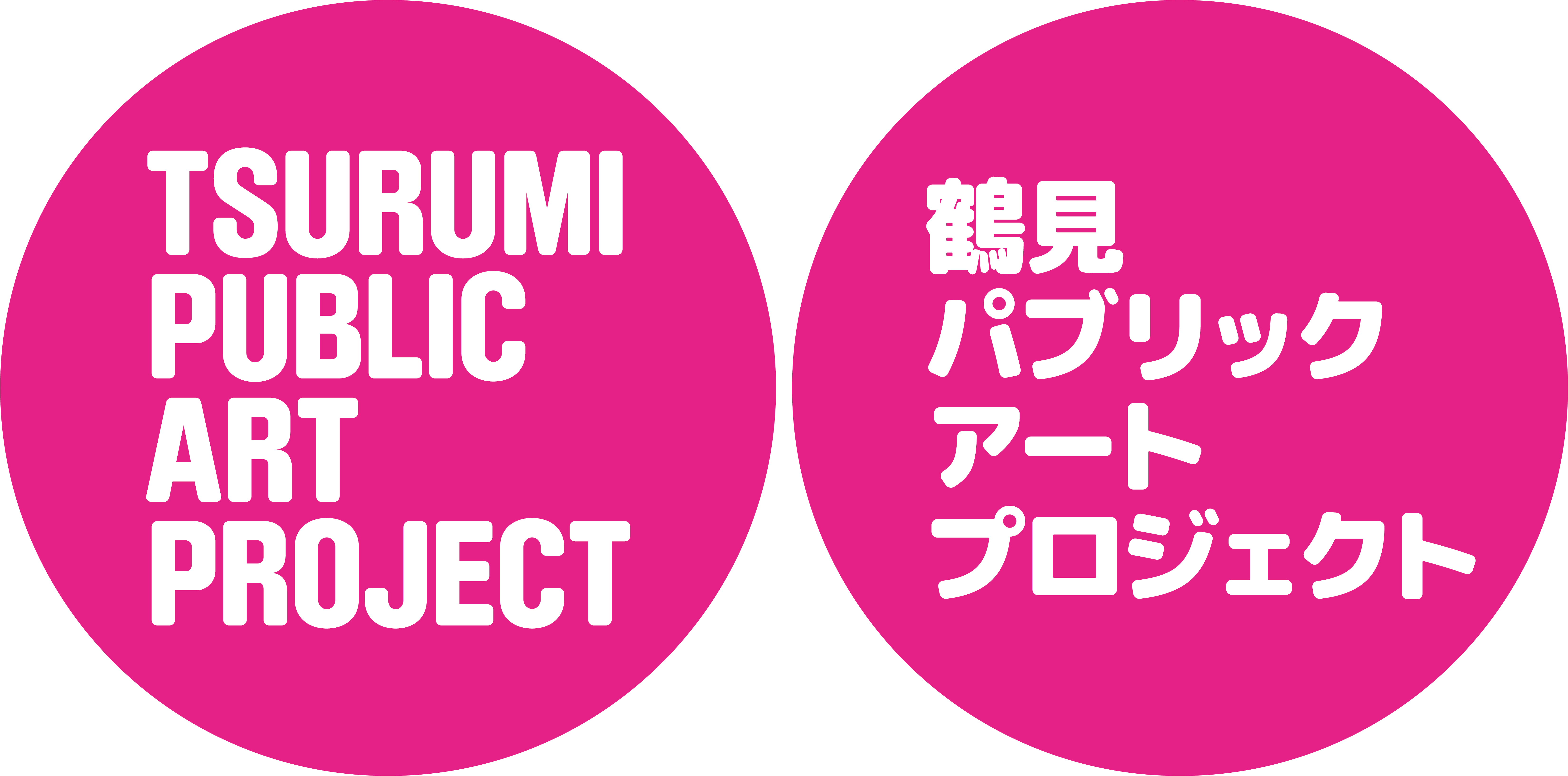
想いと装いを縫い合わせる
by 北山 深雪
小杉縫製代表取締役の小杉 清(きよし)さん
JR鶴見線・鶴見小野駅より徒歩10分の小杉縫製さん。本町通商店街で1966年に開業しました。現在もその職人技と実直なお人柄で、なくてはならない縫製の駆け込み寺のような存在です。
父の代からのミシンと共に
創業者で先代の父と同じく東京神田の仕立て屋で修行し、現在は代表取締役の小杉清(きよし)さん、弟の雅(ひとし)さん、清さんの妻の三人で店を続けています。幼い頃より父がミシン掛けをする姿を見て育ち、当時では珍しいドイツ製「PFAFF(パフ)」の黒光りしたミシンと共に父を懐かしく想い出します。
小杉縫製では、こだわりと愛着のあるリーバイスのジーンズのポケットに空いた穴を繕ってほしい、卒業まであと一年で新品を買うのは厳しい学生服のズボンのウエストを5㎝大きくしてほしい、といったさまざまな要望に日々対応しています。ズボンのウエストを5㎝小さくすることもできます。
長年通う方やご近所の方、最近ではインターネットで調べ初めて訪れる方も。その職人技と気さくなお人柄で頼りにされ、企業からの仕事依頼も引き受けています。
「形見を着たい」「自分でリメイクしたい」さまざまな要望を実現
「母が手づくりした形見のプリーツスカートをブレザーにリメイクしてもらいたい」。取材時に見せていただいた作業中の服には穴が空き傷みも多く見られましたが、お客様の熱意に触れ、穴つくろい・柄合わせ・裏地付けなど、持てる技を全て注ぎ込みます。添えられたボタンとブローチも小杉さんの思い遣り。想い出が大切によみがえり、「お客様に喜ばれるのが一番嬉しい」と話す柔和な笑みは温かさを感じます。
「着物を自分でリメイクしたい。ズボンとベストをつくりたい」。ご近所に住む青年は、ミシン掛けも初めて。それでも大丈夫。小杉さんに教えてもらいながら見事にズボンを完成させ、そのズボンを履きながらベストづくりに励んでいました。
子どもたちや商店街の仲間との交流
下野谷小学校の子どもたちがお店を訪問してくれたことも。アイロンやミシンが珍しく、興味を持ってくれ交流した楽しい想い出もあります。
趣味はスキー。スキー場ではリフト終了時間まで滑り続けるほど大好きだそうです。商店街の仲間とスキー旅を愉しむためにも仕事に励んでいる、と笑みがこぼれます。
装いは巡り合い
「お店にある豊富な糸を使い切りたい」。多種多様色とりどりの糸を眺めながら小杉さんの熱い想いがひしひしと伝わります。この糸たちは、どんな生地に出合いどんな人に出会うでしょう。人と糸と生地とのいろいろな巡り合いを縫い合わせてきた小杉さんからは、優しさが滲み出ています。
目の前のお客様のために、一日一日の仕事に集中し、充実した毎日を送る小杉さん。多くの上質な専用ミシンと共に、立派な刺繍専用ミシンも出番を心待ちにしています。
みなさん小杉縫製さんで、さらに装いを愉しみませんか。
有限会社小杉縫製
鶴見区本町通2-76
9:30〜17:00(日曜休み・不定休)
045-521-6257
洋服のお直し、穴つくろい、かけはぎ、サイズ直し、制服やジーンズの裾上げ、着物や洋服のリメイク、ネーム刺繍など
取材・文:北山 深雪
写真:鶴見小野編集部